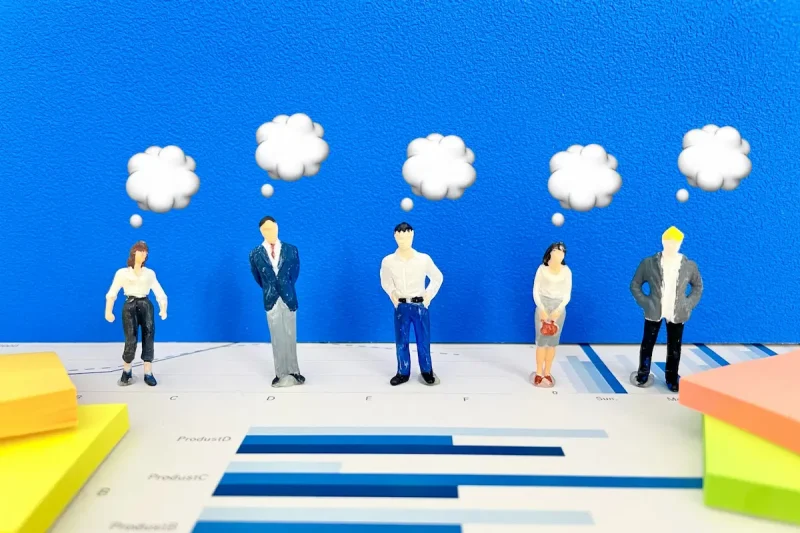新入社員の離職率が高いのはなぜ?離職防止のために企業ができる取り組みを解説

新入社員の早期離職率は約3割にのぼるといわれ、一般労働者と比較すると高い割合となっています。新入社員の離職が多い企業には人材の流出だけではないさまざまなデメリットや悪い影響が懸念されるため、離職防止に取り組みたいところです。そこで本記事では、新入社員の離職率が高い理由、離職防止のために企業ができる取り組みなどを解説します。
目次
離職防止とは

離職防止とは「リテンション」または「リテンションマネジメント」と呼ばれることもある、文字通り従業員の離職を防ぐために行われる施策のことです。従業員の離職は多方面に影響を与える可能性があり、特に新入社員の離職は企業にとって損失となる要素であるため、離職防止は企業が取り組むべき課題だといわれています。
新入社員の離職率
厚生労働省が公表している令和3年の雇用動向調査の資料によると、短時間労働者を除いた労働者である一般労働者の離職率は、11.1%でした。これに対し、厚生労働省が公表している「新規学卒就職者の離職状況」の調査によると、令和3年度の新入社員の3年以内の離職率は、新規高卒就職者が38.4%、新規大学卒就職者が34.9%で、実に3人に1人以上の新入社員が退職しています。なお、中学卒就職者に至っては50.5%と、半数以上が3年以内に退職しています。
これらのデータで一般労働者と新入社員の離職率を比較しても、新入社員の離職率が3倍以上にものぼることがわかります。 離職率は、産業によっても大きな差があります。高卒、大卒いずれも最も離職率が高かったのは宿泊業・飲食サービス業で、高卒者で65.1%、大卒者で56.6%と高い水準でした。生活関連サービス業・娯楽業が次いで離職率が高く、いずれも半数を超えています。
新入社員が早期離職する主な理由

新入社員が早期退職をする理由は、複数あります。早期退職者には一人ひとり異なる離職理由がありますが、なぜ一般労働者よりも新入社員の定着率が低いのか、その中でも多い理由として以下の5点が挙げられます。
理想と現実のギャップが大きかった
就職先の企業に対して入社前にイメージしていた理想と、実際に働き始めてからの現実に大きくギャップがあることが、新入社員の早期離職で多く見られる理由です。
最初はポジティブなイメージを持っていた新入社員が、仕事を続けていくうちに想像よりも仕事がおもしろく感じない、仕事をうまく進められないなどのネガティブな印象を持つようになるケースは、ギャップの要因となります。理想と現実のギャップが大きければ大きいほど、早期離職につながる可能性が高くなります。
労働条件に不満があった
労働条件も、早期離職につながる要因です。熱心に仕事に取り組んでいるにもかかわらず正当な評価をされない、頑張りが収入につながらないなどの労働条件に不満を抱えていると、退職してもっと良い条件の企業へ転職を考えるきっかけとなるでしょう。
給与に関する不満以外にも、思うように休暇が取れなかったり残業が多かったりする職場環境も、早期離職につながる恐れがあります。
仕事内容が合わなかった
就職前に仕事内容を理解していたつもりでも、実際の業務が自分に合わないということは新卒者には十分あり得ることです。就職前は興味や関心があった仕事であっても、仕事を始めてみると自分に合う仕事ではなかったりおもしろさが感じられなかったりすると、このままこの仕事を続けられないと感じてしまい、退職につながってしまいます。
人間関係が悪かった
新入社員に限らず、職場の人間関係は問題になりがちです。新入社員の場合は特に同僚や先輩との関係が良くないと仕事に関する相談がしづらく、仕事を進める上で支障が出る可能性があります。コミュニケーションが円滑に取れない人間関係の悪さは、離職につながりやすい要素といえます。
社風や職場環境が悪かった
社風や企業文化が合わないと感じることも、早期離職の要因に挙げられます。これらは就職前にある程度把握はできるものの、実際に働き始めなければ分からない部分も多々あります。それを目の当たりにして、「自分には合わない」と感じてしまうと、長く働けない環境と感じることがあるでしょう。
前述した人間関係の悪さともつながる要素ですが、社風や企業理念・企業文化が関係する職場環境は簡単に改善できるものではないため、継続して働ける環境ではないと判断し、離職を検討する要素となることが多くあります。
新入社員の離職が増えることで起こり得る問題

新入社員が離職することは単に人材が不足するだけにとどまらず、企業に大きな影響を与えかねない問題となります。新入社員の離職が増えると、以下のような問題が起こる可能性が考えられます。
従業員への業務負担の増加
新入社員にも担当業務が割り振られていますが、離職によってその業務の担当者がいなくなると、他の従業員が担当しなければなりません。割り振られた業務以上の負荷が従業員にかかるため、業務負担が増加してしまいます。
業務負担の増加は、従業員一人ひとりにかかる負担が重くなり、残業や休日出勤が発生することもあるでしょう。すると残された従業員のパフォーマンス低下やサービスの質低下につながり、業務負担の重さから他の従業員も離職を考える悪循環に陥ることも十分考えられます。
採用・教育コストの損失
新入社員の採用や教育には、求人媒体への掲載や選考、採用後の給与などさまざまなコストがかかっています。就職みらい研究所が公表している就職白書によると、2020年卒1人あたりの平均採用コストは93.6万円で、前年よりも増加していました。平均コストを見ただけでも、採用には少なくはないコストがかかっていることがわかります。
このような人材確保にかかる採用コストは新入社員が入社後に成果を出すことで回収が期待できますが、コストをかけて採用・育成した新入社員がすぐに退職してしまうと、それまでかけていたコストがすべて回収不可能となり、無駄になってしまいます。
教育コストは、新入社員が一人前になるためにかけるものです。一人前になる前に早期退職されてしまうと、採用コストとともに教育コストもそのまま損失となるのです。
人材採用の時間とコスト負担増加
前述したように人材採用にはコストがかかりますが、同時に時間もかかります。早期退職した従業員の穴を埋めるために新たに求人を出し、選考を経て面接、採用と一から採用活動を始めなければなりません。そのためにかかるコストとともに、一連の人材採用のために時間もかかり、企業にかかる負担が増加します。
企業イメージ悪化
新卒者の離職者が多い企業は長く働き続けることが難しい企業と判断され、離職者の多さも企業のイメージが悪化する原因となります。近年はインターネットで企業の評判や口コミを容易にチェックできるため、就活生や求職者が仕事を探す際に「新入社員の離職が多い」という情報を目にした場合、職場環境が悪かったり激務が続いたりする印象を与えてしまい、志望者が減少する原因にもなるでしょう。
離職者が多い企業は就活生や求職者に対するイメージが悪くなるばかりか、一般的なイメージにも悪影響を与えます。一度付いたネガティブなイメージは、修復することが簡単ではありません。「ブラック企業だから離職者が多いのでは」という印象が広まると、顧客や取引先にもその情報が広まることが考えられます。その結果、自社への信用性を失うこともあり得るのです。
離職する可能性が高い従業員に見られる特徴

今の仕事や職場での様子で、離職を考え始めているかどうかが判別できることがあります。以下でご紹介する様子が見られる場合、その人は離職を検討している可能性が高いといえるでしょう。
退社時間が早くなる、欠勤や有給休暇消化が増える
離職を考えている人は、次の仕事を探すために仕事と並行して転職活動を行っていることが多くなります。通常業務中に転職活動を行うことが難しいため、退社時間を早めたり欠勤、または有給休暇を消化したりして転職活動に当てることが増える傾向があります。
退社時間が早い、または欠勤や有給休暇消化が増える従業員がすべて転職を考えているとは限らないものの、このような様子が見られた場合は、転職を考えている可能性は高いでしょう。
従業員とコミュニケーションを取らなくなる
離職を考えはじめると、今の職場や仕事内容への関心が薄れていきます。本来、業務上コミュニケーションを取らなければならないにもかかわらず、他の従業員とコミュニケーションを取らなくなっている場合、転職を検討しているときの特徴だと考えられます。
今まで他の従業員とコミュニケーションを取りながら明るく仕事に取り組んでいた人が、突然コミュニケーションが減ったり挨拶をしなくなったりするなどの変化が見られた場合も、今の仕事に不満を感じ、次の仕事や転職先の方への関心が高くなっている兆候といえるでしょう。
仕事に対するモチベーションが下がっている
離職を検討し始めると今の仕事や職場への関心がなくなるため、今取り組んでいる仕事に対するモチベーションが下がるのが一般的です。仕事への集中力も下がることが多いため、仕事の質が下がりミスも増えます。ミスを指摘してもなかなか改善しなかったり、反省する様子も見られなかったりするのも、今の仕事への関心が薄くなっているために見られる特徴です。
離職防止のために企業ができる取り組み

新入社員の離職は、企業に悪い影響を与えるコストの損失や増加、他の従業員への負担増などの原因となるため、できるだけ防止したいものです。では、新入社員の離職を防止するために企業はどのような取り組みを行えばよいのでしょうか。企業が行うべき施策を解説します。
採用の時点でミスマッチを防ぐ
新入社員の離職を防止するためにまず企業が行いたいのが、採用時点でのミスマッチを防止することです。就活生や求職者が仕事を探す際は企業のホームページに記載されている会社案内や事業、業務内容をチェックして、その企業の様子を把握します。また、説明会や面接時の話を元に、その企業で働いているイメージを持つものなので、人事担当者はまず企業理念や会社の方針などを含む企業情報を公開する際に正しい内容を明確に伝えることが重要です。 あらかじめ正しい内容を伝えておくことで、入社後のミスマッチを防ぐ効果が期待できます。
入社後のフォロー体制を手厚くする
新入社員の不安や不満、疑問を解消できるよう、フォロー体制や育成体制を手厚くするのも、離職を防ぐ取り組みの一つです。
新入社員のフォロー方法にはいくつかありますが、代表的な方法が「メンター制度」を活用する方法です。メンター制度とは、新入社員1人に対して入社時期が近めの先輩社員が部下の相談役となる制度です。上司よりも気軽に仕事に対する不安や疑問、悩みなどを先輩社員に気軽に相談できる環境で新入社員のサポート体制ができるので、一人で問題を抱えることを防いで仕事に取り組めます。
メンター制度とともに、新入社員のモチベーションを維持するためには育成体制を強化して新人研修やOJT研修、1on1などを実施しましょう。育成体制の強化で離職防止効果を得られた事例があるほどなので、教育体制を充実させることは離職を防止して定着率を高めるためのポイントの一つとなります。
仕事を進める上で必要となるマナーや新しい知識、スキルを身につけて成長の機会を与えられることで、入社時の高いモチベーション維持が期待できるでしょう。
正当な評価をする
自分の働きに対して正当な評価が受けられないと、従業員は企業に対して不満を感じる要因となってしまいます。会社の評価は給与につながる要素であるため、ここで働いていても評価されず昇給も期待できないと感じてしまうでしょう。
従業員一人ひとりの働きを正当に評価するためには、人事評価制度の見直しが必要です。年功序列よりも、入社時期に関わらず成果をきちんと評価する、評価制度を開示するなど、オープンですべての従業員が納得できる評価制度を整備して正当な評価をするよう努めましょう。
社内コミュニケーションを活発化させる
社内のコミュニケーションが不足すると、従業員は仕事の悩みや不満などを相談ができる環境がなくなってしまいます。従業員が悩みや不満を一人で抱えてしまうことがないよう、常に従業員同士が活発にコミュニケーションを取れる環境を作りましょう。
前述のメンター制度以外でコミュニケーションを活発にする方法として、社内SNSの導入や社内イベントの開催などがあります。このようなツールやイベントを通して普段からコミュニケーションを活発化することで社内の雰囲気を向上させれば、職場環境の改善も期待できるでしょう。
労働環境を見直す
入社してみたら事前に聞いていた労働環境とまったく違っていた、残業や長時間労働が常態化していて定時に帰ることができないなどの労働環境の悪さは、新入社員の早期離職に直結します。ワークライフバランスが重要視されている昨今、プライベートの時間を十分に取れない労働環境は、不満を抱える大きな要因となります。
早期離職を防止するには、労働環境を見直して常態化している残業や長時間労働の削減に取り組みましょう。なぜ残業や長時間労働が増えているのかを分析し、業務効率化に取り組んで労働環境改善を行いましょう。
面談や相談を実施する
メンター制度とは別に、上司との定期的な面談の実施や相談窓口の設置なども、新入社員との信頼関係を築きやすくなる方法の一つです。話せる機会がないと、新入社員は不満や問題を抱えるばかりです。そこで定期的に面談や相談が実施できる機会を設けることで、不満や問題を溜め込むことなく相談ができ、その内容を元に改善につなげられます。
福利厚生を充実させる
ワークライフバランスが重要視されている中、働きやすい環境づくりのための福利厚生も重要なポイントとされています。福利厚生が十分ではない、利用できる福利厚生がない企業は、「従業員のことを考えていない」と判断され、ネガティブな印象を持たれてしまいかねません。つまり、福利厚生も従業員が不満を抱える原因にあるのです。
そこで福利厚生を充実させることで、従業員の満足度が向上する効果が期待できます。企業に対する満足度が上がれば、生産性の向上も期待でき、良い成果を出してもらえるため、離職を考えることも少なくなるでしょう。
福利厚生が離職防止に効果が期待できる理由

企業が新入社員の離職を防止する方法は、前述したようにいくつかの方法があります。主に職場環境や労働条件の改善が離職防止のための方法で主となりますが、福利厚生の支援も離職防止に効果的です。では、なぜ福利厚生が離職防止に効果を期待できるのでしょうか。
従業員満足度がアップするから
企業が従業員に提供する福利厚生には、住宅手当や食事補助、健康管理などがあります。福利厚生が充実していると、従業員は働きやすい労働環境を得られる上、金銭的な負担も削減できます。
その結果、会社に対する満足度が上がり、「この会社で働き続けたい」と感じてもらえるでしょう。
ワークライフバランス改善効果が得られるから
企業が従業員に提供する福利厚生は、休暇制度や旅行レジャー優待など、プライベートに関わるものも含まれます。仕事中に限らず、しっかりと休暇を取って余暇を楽しめる福利厚生があれば、従業員はワークライフバランスが取れるでしょう。
従業員のプライベートが充実していれば仕事に対するモチベーションがアップして良い成果を出す効果を得られ、離職防止効果も期待できます。
従業員の帰属意識を高められるから
「帰属意識」とは、集団や組織の一員であるという意識や感覚を指す言葉です。企業においては、従業員が勤務先企業の中に含まれていると自覚すると勤務先に対する愛着が増し、同じように帰属意識の強い従業員が集まることで協力体制が生まれます。
福利厚生がしっかりしていれば帰属意識を持つきっかけができ、他の従業員と協力して仕事に取り組める雰囲気や働きやすい職場環境が生まれます。帰属意識は会社のために成果を出したいという思いを強くするので、従業員は仕事へのモチベーションを高めて目標達成や期待以上の成果を出すために努力できるでしょう。つまり、帰属意識は企業の生産性向上に直結するというわけです。
充実した福利厚生導入は離職防止対策におすすめ

福利厚生は従業員の仕事やプライベートにさまざまなメリットが得られるだけのものと考えられがちですが、従業員のワークライフバランスを実現することが一人ひとりの従業員のパフォーマンスを向上したり、職場環境改善効果が期待できたりするため、職場に対する不満や悩み、職場環境悪化が原因の離職防止にも効果が期待できます。
新入社員の離職防止策はいくつかありますが、社内でできる対策に合わせて、従業員のワークライフバランスを改善する福利厚生も取り入れてみましょう。
まとめ
新入社員の早期離職は、採用・教育コストや従業員への負担増加、企業イメージの悪化など悪い影響が予想されます。
従業員の満足度アップが期待できる福利厚生の導入も、早期退職を防ぐための方法の一つです。新入社員の早期退職で悩んでいる企業は、採用時や入社後のフォローに加えて、ワークライフバランスや帰属意識の向上を見据えて福利厚生を取り入れてみてはいかがでしょうか。
はたらく人を元気にする会社

グループ間協力で、売店・食堂・企業内福利厚生をワンストップでサポートいたします。売店とカフェの併設や24時間無人店舗など、個々の会社では難しい案件も、グループ間協力ができる弊社ならではのスピード感で迅速にご提案します。
心幸グループ WEBSITE