備蓄米とは何?購入後の保管方法と米の備蓄方法を解説

2025年3月18日、備蓄米の放出が大きなニュースとなりました。通常は政府が災害時などに備えている備蓄米が市場に流通するのは、これが初めてのこととなります。なぜ今、備蓄米が市場に出回ることになったのでしょうか。本記事では、備蓄米の基本と備蓄米をはじめとした米の適切な保存方法、家庭で米を保存するコツを解説します。
目次
備蓄米とは
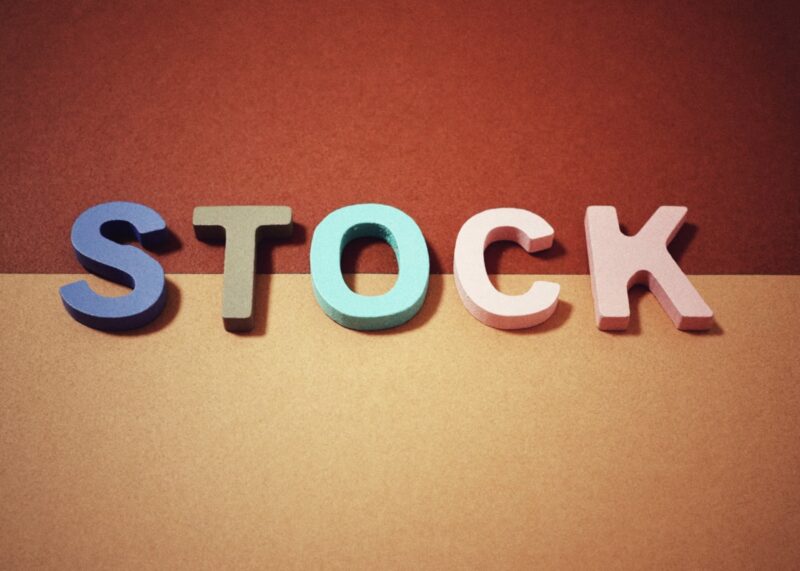
備蓄米とは、政府が国民の主食である米の凶作時の供給不足に備えて、安定的に米を供給できるよう国が保管する米のことです。1993年、記録的な冷夏により戦後最悪の大凶作となった「平成の米騒動」の際、消費者が米を求めて小売店に殺到した経験を踏まえて、1995年に米の備蓄が制度化されました。
政府は毎年2万トンの米を買い入れ、10年に一度の不作時に米を供給するために、約100万トンの米を備蓄しています。
備蓄米の保管方法
備蓄米はリスク分散のため、備蓄米は主に米の生産量が多い地域を中心として、全国各地の民間業者の施設や倉庫などに気温15度、湿度60~65度の環境で年間を通して保管されています。温度・湿度に加えてカビや害虫対策が施された適切な環境で保管されている備蓄米は、5年間もの長期間保管していても、おいしく食べられます。なお、保管期間を過ぎた米は飼料用などとして売却されます。
米の備蓄方法は、2種類あります。かつて、米の備蓄は「回転備蓄方式」という方式で行われてきました。回転備蓄方式とは、一定期間備蓄した後に古い米を市場に放出、秋のみに買い入れをして新しい米を備蓄する方式です。備蓄期間は1~2年と短いので鮮度を保ちやすい一方で、流通量が変動しがちでした。
もう一つの備蓄方法は、「棚上げ備蓄方式」です。棚上げ備蓄方式とは、米を長期間保存した後に必要な量のみを放出する方式で、5年という長期の保管期間ながら品質を維持できる上、買い入れ時期を柔軟に設定できるメリットがあります。2011年以降、備蓄米は棚上げ備蓄方式が主流となっており、今回市場に流通した米もこの方式で備蓄されたものです。
備蓄米が市場に放出された理由
2025年3月、備蓄米が市場に放出されたことがニュースになりました。これは、米の価格高騰と流通の円滑化が理由です。米の小売価格は2024年6月以降右肩上がりで上昇しており、昨年の同じ時期の約2倍も値上がりしています。これは、市場に適切な量の米が出回っていないことが原因とされているため、備蓄米を市場に放出して流通を促し、止まらない米の価格高騰の沈静化を図ったというわけです。
備蓄米は米の凶作に限らず、2011年の東日本大震災、2016年の熊本地震の際に流通業者向けに販売されるなど、災害時にも活用されています。2024年には米菓などの原料不足により、加工用米として販売されています。しかし、過去に米不足による市場への放出はなく、今回初めて政府の備蓄米が市場に放出されたことになります。
市場に放出された備蓄米が備蓄米として明示されて販売されるかどうかは、小売店の判断によります。また、備蓄米のみで販売する以外に、他の米と混ぜて販売する方法もあるため、一般の米と備蓄米は必ずしも区別して販売されるとは限りません。
〉〉いつまで続く? 米の価格が値上がりする要因と今後の上昇見通し…まるで令和の米騒動!?についてはこちら
備蓄米を購入した後の保存方法は?

備蓄米は販売時に明示されていないこともあるため、購入した米が備蓄米かどうかわからない状態であることが考えられます。そのため、購入した米は備蓄米かどうかに限らず、劣化を防ぐために適切な方法で保存しましょう。
鮮度を保つために冷暗所での保存がおすすめ
あまり意識していない方が多いかもしれませんが、お米は生鮮食品です。特に精米した白米は、適切に保存しなければ劣化してしまいます。長期保管されてはいますが、備蓄米は適切な方法で保管されている米です。一方、販売後の米は備蓄米に限らず、家庭で適切な方法で保存しなければ劣化し、味が落ちてしまいます。
お米が最もおいしいのは精米した直後で、その後は時間の経過とともにだんだんと劣化してしまいます。米の劣化は酸化が原因の一つで、気温10度以上で酸化が活発となります。さらに、15~25度は虫が発生しやすい温度であることから、およそ10度の低温が米の保存に適しています。湿度も米の保存に重要なポイントで、湿度が低いと乾燥により米が割れてしまいます。55~75%程度の湿度が米の保存にベストな湿度なので、極端に乾燥している場所、湿度が高すぎる場所を避け、一定の湿度が保てる場所に保存しましょう。
これらの条件から、家庭内で米を保存するには床下収納庫や冷蔵庫などの冷暗所に置くのがおすすめです。ただし、冷蔵庫は乾燥しやすいので、野菜室で保存しましょう。冷凍庫での保存は、米に含まれる水分が凍って米にひびが入り、米を研いだときにデンプンが流出してしまうのでおすすめできません。味や食感、栄養価が落ちる原因となるので、冷凍庫での保存も避けるべきです。
米を保存するポイント
上記の米の鮮度を保つ方法に加えて、おいしい状態で米を保存するには、できるだけ空気に触れさせないことが基本です。米保存専用の容器「米びつ」を使用してもいいですが、長期保存を見据えるのであれば、米袋に入れたままではなく密閉容器に入れて5~15度程度の温度と適切な湿度に保たれた場所で保存しましょう。密閉容器や米びつがない場合は、比較的密閉性が高く中身が見える空のペットボトルを活用するのも一つの方法です。
真空パックは米の劣化原因である酸素や湿気を防げるので、米の保存におすすめです。真空パックなら常温で約1年、冷蔵で約2年の長期保存も可能です。真空パック保存の注意点は、暑い時期の保管場所です。真空パックにしていても高温下で保存すると味が落ちてしまうので、特に暑い時期は冷蔵庫で保存しましょう。
また、米は臭いを吸収しやすい特徴を持っています。臭いが強いもののそばに置くと臭いが染み込んでしまいます。味に直接変化はないものの、臭いが付いたままではおいしく食べられません。臭い移りを避けるためには臭いの強い食品や洗剤、灯油などの近くでの保存は避けましょう。
できれば玄米か無洗米で保存
市販の米を購入する際は、精米された白米を買う方が多いのではないでしょうか。日常的に食べる米は研いで炊けばすぐ食べられる白米が一般的ですが、すぐに食べずに保存する場合は、白米よりも玄米か無洗米での保存がおすすめです。
その理由は、精米前の玄米は、食べる前に精米するので味が劣化しにくい特徴があるからです。また、無洗米も米の劣化の原因である脂質が含まれている糠(ぬか)が取り除かれているため、白米よりも酸化しにくいといわれます。そのため、備蓄用として米を長期保存するなら、玄米か無洗米を選びましょう。
家庭で米を備蓄するには
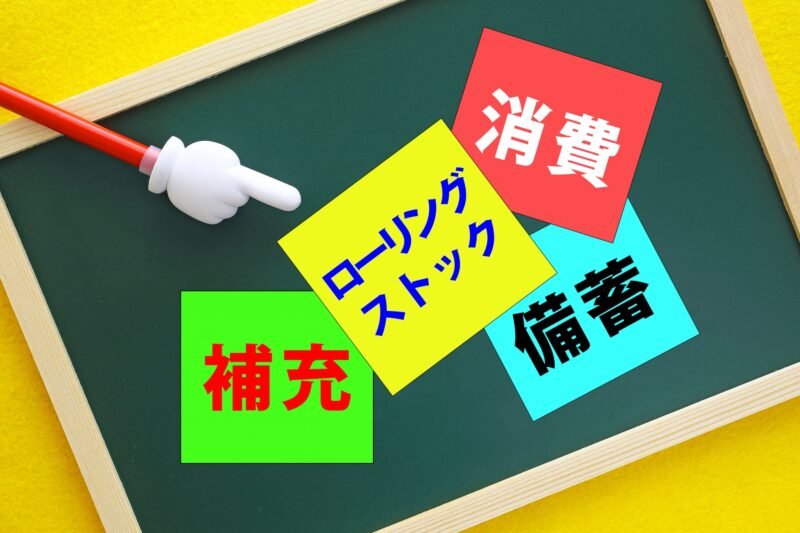
日本の主食である米は、家庭において重要な食品の一つです。日常的に食べる食品だからこそ、非常時に備えて米は備蓄しておきたいものです。そこで、家庭で米を備蓄するために覚えておきたい2つのコツを解説します。
ローリングストックで効率良く備蓄
家庭での米の備蓄には、食べながら備蓄をするローリングストックが最適です。農林水産省でも、災害時の備蓄方法としてローリングストックを推奨しています。
ローリングストックとは、食品を多めに買い置きして古いものから消費し、消費した分を買い足しながら常に一定量の食品を備蓄する方法です。普段食べている食品を消費しながら備蓄するのが、常に備蓄しておく非常食とは異なります。
非常食のように長期保存が不可能な米は、消費した分を買い足すローリングストックでの備蓄が最適です。
備蓄量の目安
ローリングストックでの備蓄量の目安は、最低でも3日、できれば1週間分です。これは、災害発生からライフライン復旧までの期間を想定し、1週間程度はスーパーやコンビニで食料を確保できなくなることを想定しています。つまり、米は家族の人数分を1週間分備蓄しておくのが望ましいといえます。
米1合で炊きあがるごはんの量は約350g、茶碗1杯分の米はおよそ140gなので、米1合で約2.5杯分のごはんを炊けます。1人あたり1日2杯のごはんを食べると仮定すると、1週間分で1人あたり5.6合、2人家族なら11.2合です。米1合が約150gなので、2人家族に必要な米の備蓄の目安はおよそ1800gとなります。
この量を参考にすると、2kgの米を消費しながら買い足していけば、効率的に2人で1週間分の米をローリングストックで備蓄できるでしょう。
1カ月以上保存するには玄米がおすすめ
前述の通り、米を長期保存するには白米よりも精米前の玄米の方が劣化しにくく保存しやすいのでおすすめです。1カ月以上保存するなら、玄米の状態で密閉して冷暗所に置けば、長期間保存できます。
常温で1カ月以上玄米を保存する際は、衣類圧縮袋などの密閉できる袋に入れて空気を抜いて保存しましょう。密閉袋の中に脱酸素剤、または脱酸素剤代わりとして使える使い捨てカイロを入れて置くと、袋の中の酸素を取り除きながら虫が付くのを防げます。適切な方法で保存された玄米は、精米すれば購入したばかりの白米とほとんど変わらずに味わえます。
まとめ

現在流通が開始されたばかりの備蓄米は、適切に管理・保存されているものなので、基本的に一般的な米と同様においしく食べられるものです。しかし、購入後の米は家庭で適切に保存しなければ、おいしさが維持できず長期間の保存も難しくなります。家庭でも非常時に備えてローリングストックで米を保存する場合は、今回ご紹介した適切な米の保存方法や長期保存のコツを押さえて、いざというときのために必要な量の米を備えておきましょう。
食べながらそなえる、新しい備蓄

オフめしイート&ストックは、賞味期限が製造から約1年あるオフめしの「常温そうざい」を利用した、普段は食べながらそなえる、新しい備蓄プランです。
オフめしEAT&STOCKはこちら


